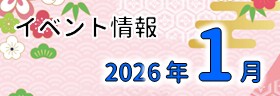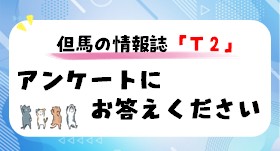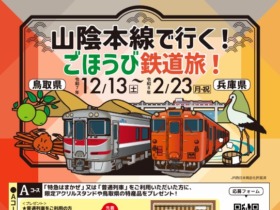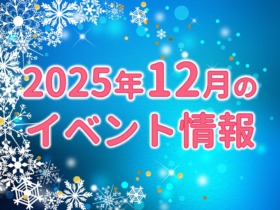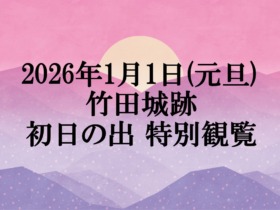兵庫県朝来市にある新井地区は、江戸時代に伊能忠敬が記した測量日記によると、30~40軒の農家がある小さな村でした。
その後、播但線の新井駅が開業すると神子畑鉱山や選鉱場の恩恵を受けるようになり、わずか10~20年で但馬でも有数の近代的な町へと発展しました。
それでは、大正から昭和にかけて鉄道の町として栄えた新井地区を散策してみましょう。

スタート地点であるJR播但線新井駅駅舎です。
1901年(明治34)、播但鉄道の終着駅として新井駅が開業しました。
私設鉄道である播但鉄道は、生野鉱山から姫路・飾磨港を結んだ「生野鉱山寮馬車道(銀の馬車道)」を補う新たな輸送手段として敷設されました。
一方で、神子畑鉱山からは神新軌道と呼ばれる鉱山鉄道が新井駅まで敷設され、新井駅はターミナル駅として栄えます。
まだ、但馬に山陰本線がひかれる前の開業なので、播但線の開通がいかに重要であったかが分かります。

新井駅を出ると左手に朝来市営駐車場があります。
駐車場が周辺より少し高くなっているのは、この場所に貨物用の上屋やクレーンがあり、鉱石の積み替えが行われたホームの名残だそうです。
当時、神子畑から鉱石を運ぶ神新軌道は、途中で木材運搬用の軌道も合流し、駅まで播但線と並行して走っていたそうです。

大正から昭和にかけて、明延鉱山で産出された鉱石は、明神電車で神子畑選鉱場へ、神新軌道で新井駅へ、播但線で飾磨港へ、最後は船で香川県の直島製錬所まで運搬されました。
ちなみに、神子畑選鉱場は、最盛期には規模・産出量ともに「東洋一」と謳われた選鉱施設でした。
1957年(昭和32)、神新軌道はトラック輸送に切り替えられ、駅周辺のレールは撤去されていますが、鉱石や木材を積み替えるための播但線の貨物引き込み線跡は今も残っています。

新井駅前の交差点を右折し、県道70号線をしばらく歩きます。

県道70号線を4分ほど歩くと、左手に煙出しが残った趣のある古民家が見えるので、ここで左折します。
少し歩くと、但馬街道と呼ばれた旧街道に合流するので左折します。

但馬街道を2分ほど歩くと、切り立つ岩壁が出現します。
その岩壁のお堂に六体地蔵が祀られています。

六体地蔵のあたりから但馬街道の趣を残した町並みを楽しむことができます。
この通りには、存在感を放つ茅葺にトタン覆いの家屋、町屋風の民家など、懐かしい佇まいの民家が残っています。
また、小高い所から見ると、細い但馬街道が民家を縫うように通っていることがよく分かります。

大正に入ると、但馬街道沿線に姫路方面から多数の商人が移り住み、急速ににぎやかな市街地が形成されました。
昭和十年代の商店街には、呉服店、酒屋、自転車屋といった商店のほかに、銀行や医院、銭湯などが並び、「新井へ行けば生活のすべてが揃う」と言われたそうです。
.jpg)
六体地蔵から3分ほど歩き、写真のポイントで右折します。

少し歩くと、金毘羅神社に到着します。
ここで春には金毘羅大祭が行われます。
また、桜の名所としても知られています。

金毘羅神社の隣には、金毘羅遊園跡の公園があります。
大正時代、この公園で朝来郡内のテニス大会が行われたそうです。

公園の一角には「金毘羅遊園」と刻まれた碑があります。

昭和の初め頃まで、公園の脇にある通りは、鉱山夫や町の人が集まる娯楽の中心地で、芝居小屋、ビリヤード場、カフェなどモダンな店舗が並んでいたそうです。
ここをまっすぐに進むと再び但馬街道に合流するので、突き当たりを右折します。
.jpg)
但馬街道を少し歩くと三叉路があるので、左折します。
.jpg)
1分ほど歩くと県道70号線に合流するので右折し、次の信号のある交差点を左折します。

左折ポイントの一角に謎のモニュメントがあります。
このモニュメントは、朝来町ライオンズクラブが1999年(平成11)に設置したもので、地元の芸術家が「子どもは風の子」
をテーマに制作されたそうです。
新井駅が最寄り駅であるあさご芸術の森は、野外アートで知られていますが、ここでもアートなまちの一面が感じられます。
関連記事 2020.10.27投稿
あさご芸術の森で色づきはじめた紅葉と芸術を満喫
.jpg)
踏切に差し掛かったところで、左手を見ると、神新軌道跡と言われる細長い路地が続いています。
ちなみに、奥に見える跨線橋が新井駅です。

踏切を渡り、少し歩くと円山川に架かる新橋が見えてきます。
橋の欄干にナマズのモニュメントがありました。
ナマズと言えば地震が連想されますが、この地域はナマズと何か関係があるのでしょうか?

橋の欄干から踏切付近まで戻ると、今回の散策のゴール地点である白髭神社に到着します。
ここで先ほどのナマズのモニュメントの謎が解けました。
白髭神社にまつわる言い伝えと関係があるようです。

江戸時代、この地域では円山川が何度も氾濫しました。
祟りと恐れた村人たちは、琵琶湖の白髭神社から分身を持ち帰り祀りました。
その分身がいつしか「髭」になぞらえ、ナマズが白髭神社の使いと信じられるようになり、ナマズを食べると「罰が当たる」と長年言い伝えられてきたそうです。

懸魚(げぎょ)は、火除けのまじないとして魚の形に似たものを飾ったことがはじまりのようですが、神社の言い伝えを聞いていると、懸魚の部分がナマズに見えてきました。

大正から昭和にかけて、東洋一と謳われた神子畑選鉱場や鉄道の恩恵を受けて、但馬でも有数の近代的な町へと急速に発展した新井地区。
当時の繁栄していたころの面影は年々少なくなっていますが、その面影をたどってみると、大正・昭和に一時代を築いた歴史に触れることのできるまちです。