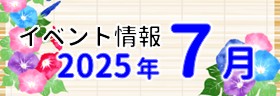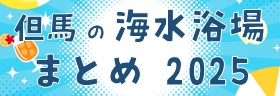新温泉町にある山陰本線「久谷駅」からのぼり方向を見ると、トンネルが見えます。
このトンネルは「桃観トンネル」とよばれ、
余部鉄橋とともに明治45年に全通した山陰本線、最大の難工事の箇所だったといわれています。
このトンネルがある桃観峠は、峠を越える難所であり、股(もも)がうずくことから「ももうずき峠」と呼ばれており、鉄道の建設に当たって、良い名をつけようということで、「もも」から「桃見峠」となり、さらに「桃観峠」という名前が付けられたそうです。
.jpg)
トンネルの全長は開通当時1991mで、山陰線で1番長いトンネルでした。
現在でも、山口県にある「大刈トンネル」についで2番目に長いトンネルとのことです。
(現在の桃観トンネルの長さは1992m)
約4年間の年月と当時の金額では61万円という巨額が投じられた工事で、当時の最先端の技術によって掘削が試みられました。
.jpg)
そのような一大プロジェクトの工事であったことの証として
桃観トンネルの入り口上部には、当時の鉄道院総裁、後藤新平の揮毫による石額が掲げられいます。
このような石額が掲げられたトンネルは全国でも数例しかないとのこと…
久谷駅側の入り口には「萬方惟慶(すべての人がこれを喜ぶ)」と刻まれています。
2.jpg)
香美町の餘部駅側のトンネル入り口です。
余部側に少し行くと、高さ41mの橋脚の余部橋梁があります。
いかに但馬地域北部の山陰線が山と谷の間を縫って通っているかがわかりますね
-.jpg)
余部駅側の石額には、「惟徳罔小(この徳は少なくない)」という文字が刻まれています。
.jpg)
久谷駅から歩いて数分のところに「八幡神社」があります。
この神社は、「ざんざか踊り」と呼ばれる兵庫県の無形民俗文化財に指定されている芸能が伝わる神社です。

その境内には、桃観トンネルの犠牲者を供養した「招魂碑」があり、
工事で犠牲となった27名の方の名前が刻まれています。

27名の犠牲者の中には、朝鮮出身の方もおられたとのことで
招魂碑には、ハングル文字のラベルの品が供えてありました。
多くの方の犠牲のうえで、現在、鉄道が運行されているのですね。

写真は、桃観トンネルと同時期に設置された浜坂駅(新温泉町)の給水塔です。
蒸気機関車(SL)に水を補給するためのものです。(明治44年設置)
このような山陰本線に関する明治時代の近代化遺産は但馬地域に多くあります。
巡ってみるのも面白いですね!
関連記事
養父市
レトロな魅力!八鹿駅と跨線橋
取材日:2019.7.26