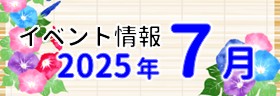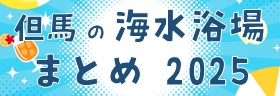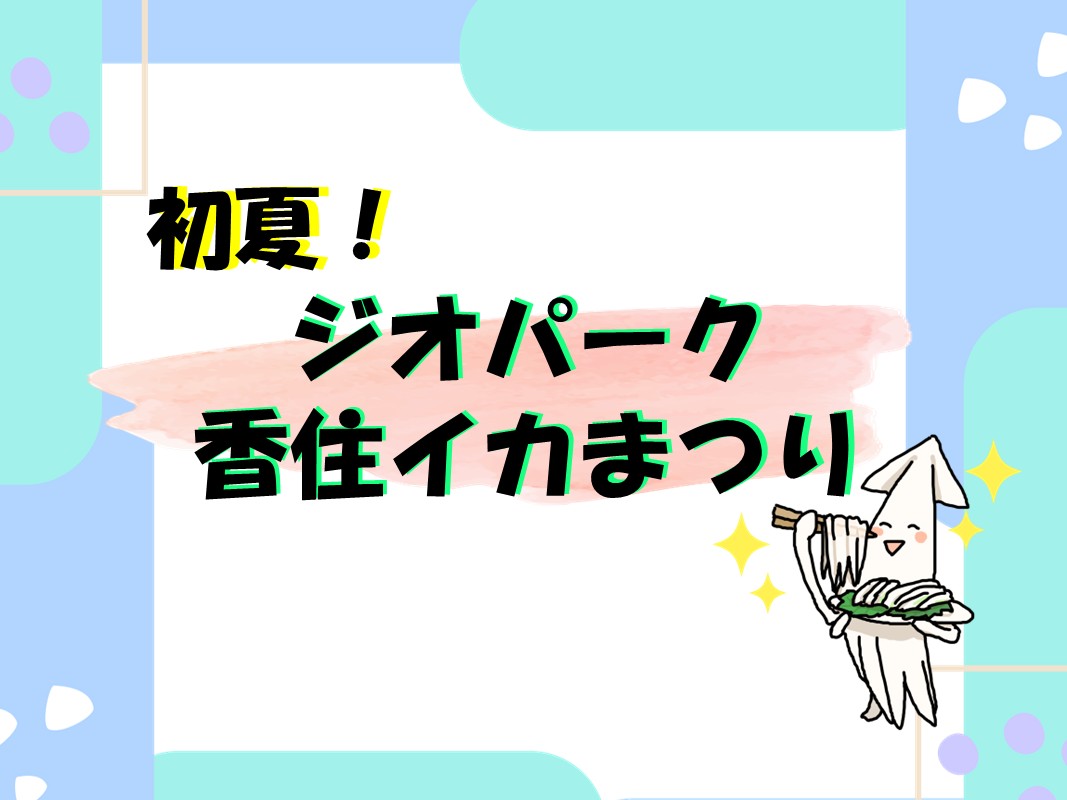※不要不急の外出自粛が要請されています。ブログの写真でお楽しみください。
但馬の駅とその周辺の見どころを併せてご紹介します。
第4回はJR山陰線「玄武洞駅」です。
円山川の左岸、国の天然記念物「玄武洞」の対岸にあり、玄武洞の玄関口だったのでしょうね。
今でも渡し船が運行されています。ぜひ一度乗ってみたいものです。
(参考のため、地図を頼りに地名を入れていますが、違っていたら御免なさい。)



開業は1912年(明治45年)3月2日です。(参照:Wikipedia)
駅を出てすぐ目の前の円山川には、渡し船の船着き場が整備されています。
定期便はなく、対岸にある「玄武洞ミュージアム(0796-23-3821)」で予約が必要です。乗船料1人300円、乗船定員10人です。(参照:豊岡観光協会HP)


特急こうのとり号がちょうどやってきましたが、ビュンと通り過ぎました。玄武洞駅には普通電車のみ停車します。
上りの次の駅は豊岡駅、下りの次の駅は城崎温泉駅です。無人駅なので、ゆっくりと見学させてもらいました。


駅の対岸にある玄武洞です。上の写真が「玄武洞」下は「青龍洞」で、この他にも「白虎洞」「南朱雀洞」「北朱雀洞」を歩いて楽しむことができます。
案内看板によると、「玄武洞」の命名者は江戸後期の儒学者である柴野栗山氏で、岩の断面などが妖獣「玄武」を連想することから名づけられたそうです。
ちなみに玄武は、亀に龍が巻き付いた姿をしており、玄武岩の六角形が亀の甲羅の模様に見えたんでしょうね。

駅のすぐ南に位置する二見には幾つかの文化財があります。まずその一つ、「二見の清水」です。蛇口が取り付けられ、汲むことができます。玄武洞の名付け親である柴野栗山氏は、この清水を「無限水」と命名しています。

この地域には4基からなる二見谷古墳群があり、県指定史跡に指定されています。
この内、写真の1号古墳は直径20m余りの円墳で、家形石棺を伴い、圭頭大刀の杷頭・刀子・管玉・耳環などが見つかっています。6世紀後半ごろに築造され、7世紀以降、複数回にわたって追葬や追善供養が行われました。(参照:Wikipedia)

二見をさらに、ずっと南下して豊岡市滝という地区には、「小沼の滝」があります。
玄武岩の黒々とした岩肌を、白い鮮烈な滝が流れ落ちていきます。
玄武洞と同じく、ここも火山活動がもたらした素晴らしい景観の一つです。


今度は駅を北上すると、来日の集落の入り口、堂々辻に「但馬六十六ヶ所地蔵霊場 第55番札所」があり、集落により大切にお祀りされています。
札所ごとに地区の名前を読み込んだご詠歌があります(下の写真)。「ニッポンの霊場」というHPで、こちらのご詠歌を参照してみました。
苦しい(くるひ)も なにと思うて 人船も 冥途の使い 発つと知らずや
ただ頼め 地蔵菩薩の 御誓願 来る日(くるひ)は後世に 近き世の人
※( )は投稿者により補足

最後はやはり来日山山頂で締めくくりましょう。
眼下を南に目をやれば、山間を流れる円山川と豊岡市街

北東には城崎温泉街

そして北西には、猫崎半島と竹野の海岸が確認できます。
玄武洞駅周辺は、自然の変化にとんだ地形を楽しむことができます。コロナ関係が収束したら、皆さんもいかがですか?
但馬はいつでも、旅人を迎えてくれます。