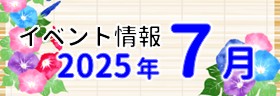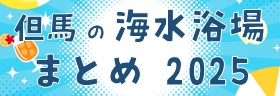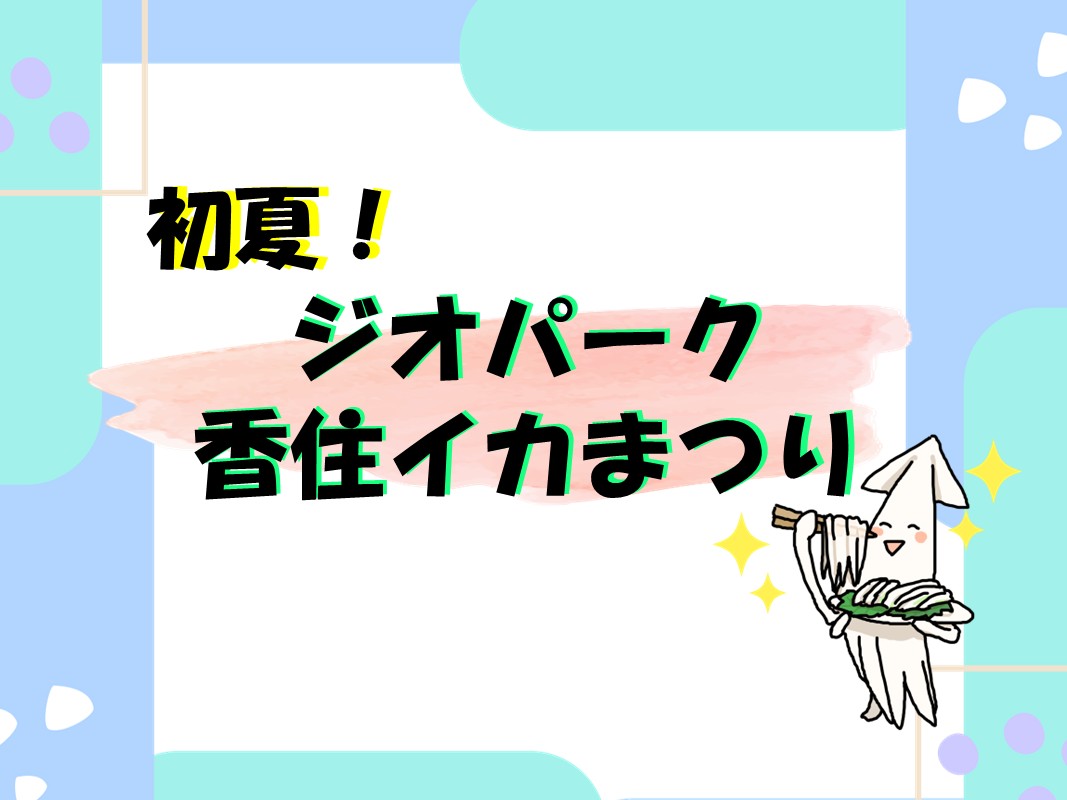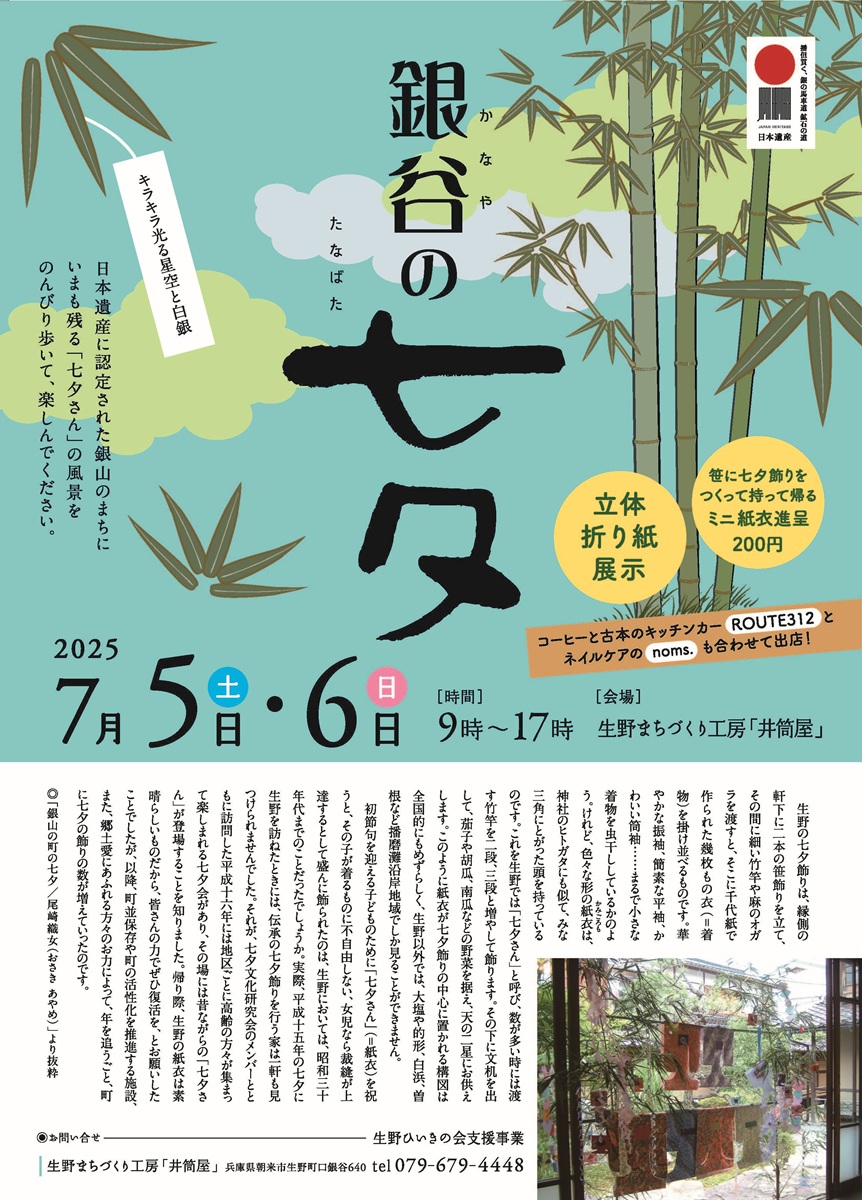朝来市和田山町寺内、山王神社(佐伎都比古阿流知命神社(さきつひこあるちのみことじんじゃ))において、
毎年7月の第3日曜日(今年は15日)子孫の繁栄と五穀豊穣・天下泰平を祈念し、奉納される太鼓踊りです。

400年間にわたり踊り継がれてきて、兵庫県無形民俗文化財に指定されています。

踊り手は茶褐色に水玉模様の山王神社の使者であるサルの装いで、腰の太鼓を叩きながら輪になって踊る「側踊り」11人います。

笠をつけて、特殊なうちわを振りつつ踊りながら全体の指揮をとる「新発意(しんぼし)」2人がいます。

輪の中心では「しない」(12か月をしめす12本の竹すだれに365日をしめす365枚の紙しでをとりつけたもの)を背につけた2人が、それを互いにからませたり、地面に打ち付けたりしながら踊ります。

音頭方3人の息の合った歌と囃子、名調子で踊り方をリードします。

「太鼓踊り」ともいわれていますが、歌に合わせて打つ太鼓の音が、あたかも「ざんざかざっとう、ざんざかざっとう」と響くこと、12種の歌のいずれにも「ざんざかざっとう、ざんざかざっとう」の囃子がともなうことから「ざんざか踊り」と名付けられたといわれています。

真夏の37℃の猛暑の中、約40分間の踊り、最後は本殿へ報告で終わります。
山王神社に奉納後は、場所を光福寺に移して奉納します。