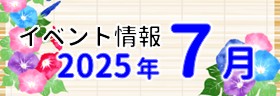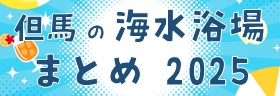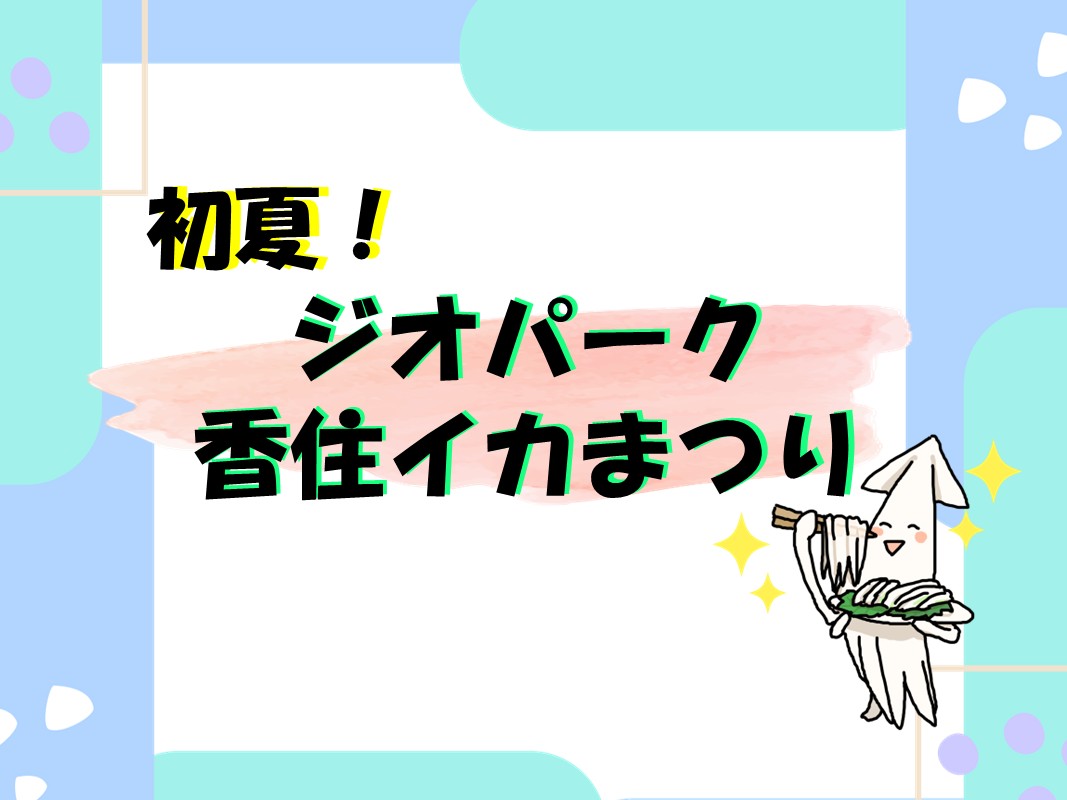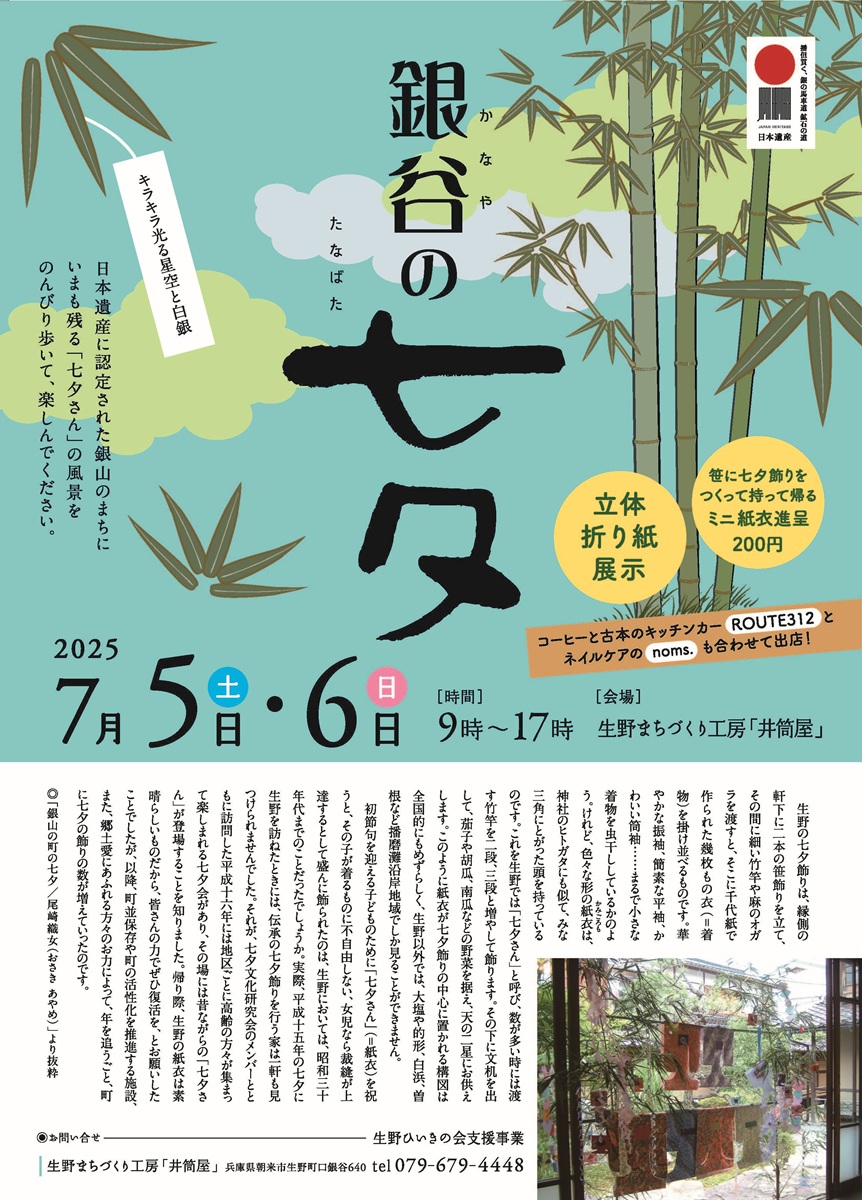毎年10月第3日曜日、和田山町宮、石部神社で江戸初期から伝わるとされる神楽の奉納が行われました。

江戸初期1647年(正保4年)、宮地区にある円明寺の石垣築造の際に、尾張からやってきた石工によって、伝授されたものといわれ。静かに神前に奉納する質素な演技が特徴であります。ゆったりとした舞いは、軽快に跳ねる勇壮な神楽獅子舞とは一線を画しています。
↓左は演舞場と富くじの景品の陳列 右は「花掛」の神楽


動画で宮神楽「花掛」の舞の一部をご覧下さい
動画が表示されない場合は、右のバナーをクリックしてAdobe Flash Playerをインストールしてください。

神楽の前に、伊勢音頭の唄に合わせて子供の練込みが行われました。

動画でその様子をご覧下さい
動画が表示されない場合は、右のバナーをクリックしてAdobe Flash Playerをインストールしてください。
刀我石部神社は、夜久野高原の山すそ、和田山町宮地区の氏神を祭る神社として、平安時代の建立。水明天皇の妻の妹と伝えられる蹈韛五十鈴姫(ヒメタタライスズヒメノミコト)(女神)を祭る神社として地域の人々に守り継がれています。
神社の門前には、絹ずりの泉と言われる湧き水が出てきています。そこには「神鯉」と言われる鯉が生息しています。


氏子総代さんのお話によれば、舞手の後継者の少ないのが悩みとのことでした。