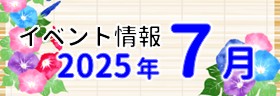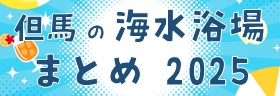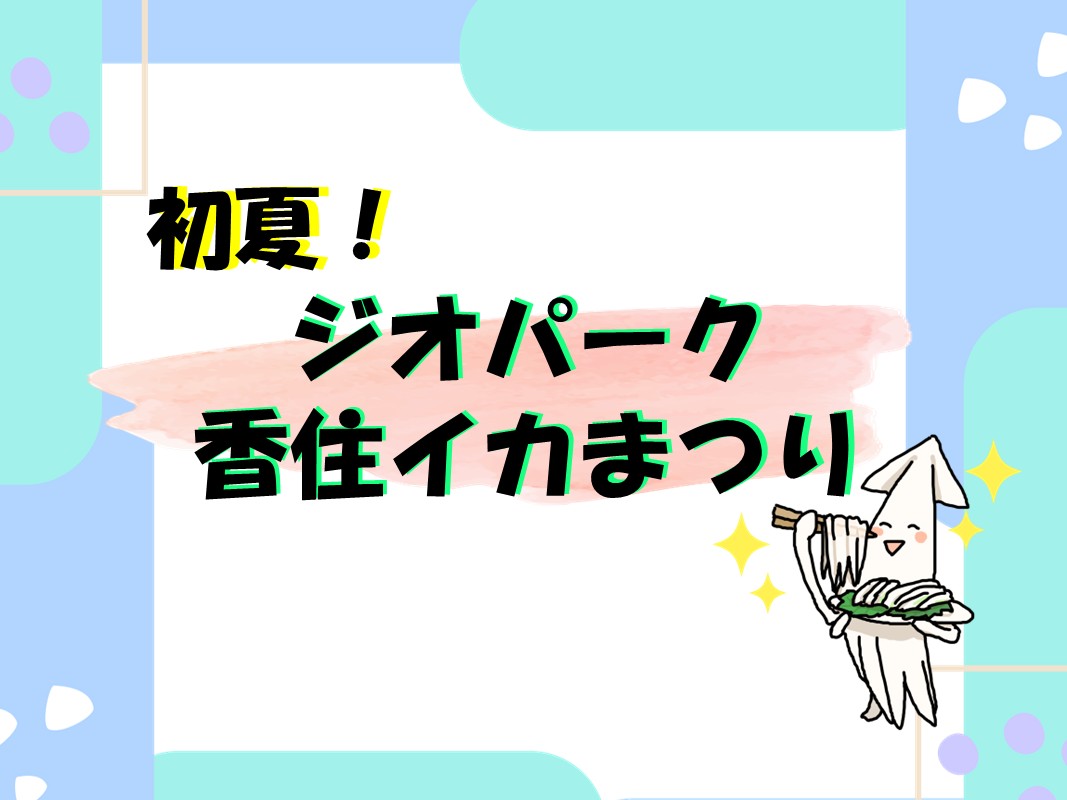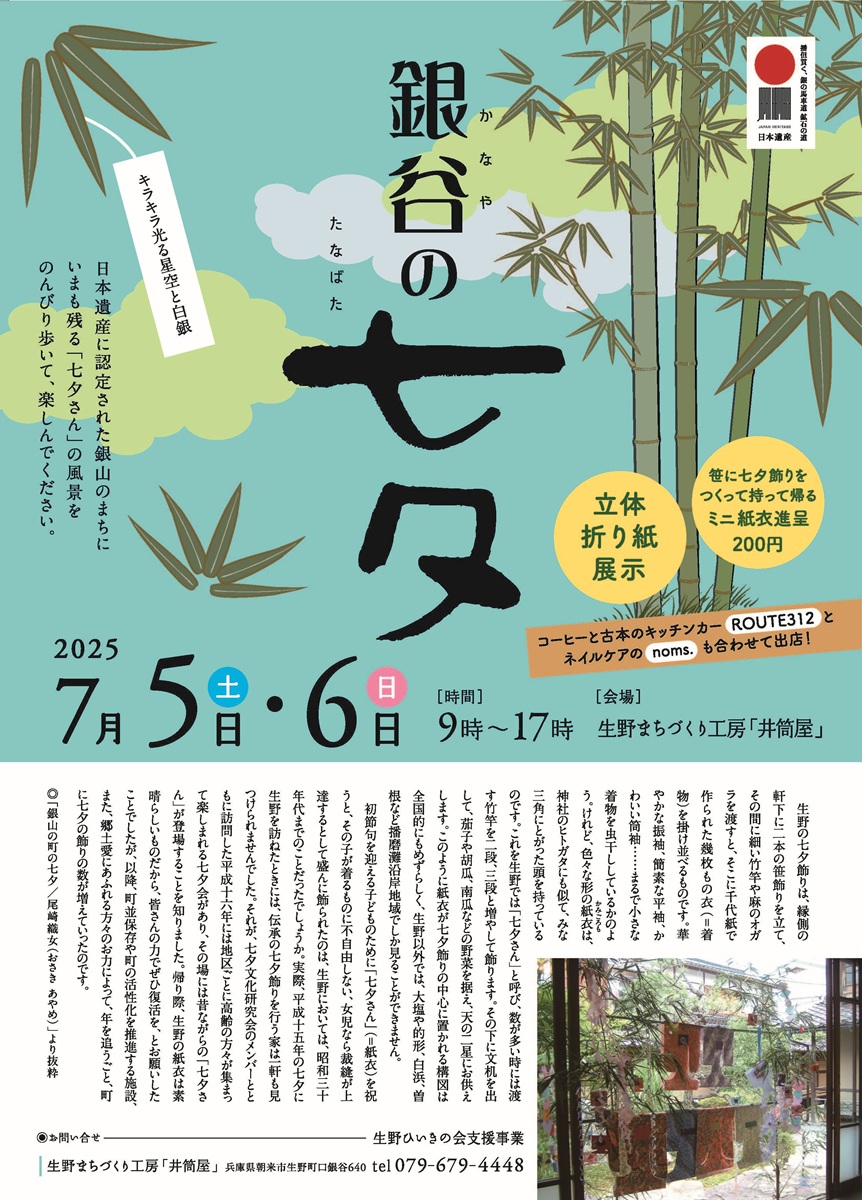但馬の駅とその周辺の見どころを併せてご紹介してきましたが、「たじま途中下車の旅」の投稿が始まりましたので、こちらは企画を変更!
「下車の旅」は概ね歩いて回る範囲の見どころが紹介されていますので、レンタサイクルや列車に自転車を輪行して行くことのできる見どころ情報をお送りします。(半径5~6キロというところです)
名付けて「駅サプリ」。サプリは「サプリメント」の略で、補足という意味です。「途中下車の旅」情報を”個人的に”補足し、またお読みくださる皆さんの心の栄養補給の足しになれば幸いです。
第9回はJR山陰線「八鹿駅」です。(先に、たじま途中下車の旅「うだつと大正ロマンの雰囲気を今に伝える町・八鹿を歩く」を見てね)
八鹿駅周辺には伝説があふれていたのであった。

八鹿駅から国道312号を豊岡方面へ北上し、上小田区の公会堂まで約1.1km。公会堂の横にお地蔵さまがお祀りされています。お堂も大きく立派です。

お地蔵さまが座る蓮華座の下の台、よく見ると文字が刻まれています。「右 いつし 左 ゆしま」
ここに安置される前、右は出石、左は城崎湯島に行く交差点におられたのでしょうか。
それにしても福福しいお顔です。どこかでお見かけしたような、、おお、そうだ!。漫才コンビ、バナナマンの日村さんに似ていると思いませんか?

お地蔵さんから、上小田区の集落を通り抜け、一番奥に350mほど進むと、木の名を冠する柳神社に到着します。
【伝説】
村人は毎日川を渡って耕地を耕し、暗くなるとまた川を渡って家に帰りました。暗闇に川を渡るのは危険ですが、浅瀬の中ほどに妖しい光が灯り、安全に川を渡ることができました。村人は不思議に思い、光っていた周辺を昼間に調べると、古い柳の株が埋まっていました。安全に渡してもらったことを感謝し、古木を祀ったそうな。(参照:T2 No112号)
このお社の中に、柳の古木が祀られているのでしょうか、、。
私の知り合い情報によると、昔、神社の裏の山には寺があり、いまでも瓦が沢山転がっているんだと、、。不思議がいっぱい。

柳が光っていたのは、あの橋のあるあたりかしらん、、と物思いにふけっていると特急コウノトリ号が走り去っていきました。

柳神社を降り、国道312号を豊岡方面に北上し、宿南の集落を流れる三谷川を上流に向かいます。神社から約3.7km、鹿柵の向こうに「掃部(かもん)之塚」があります。ここは高木掃部のお屋敷があった場所です。
【伝説】
文安(1400年代半ば)の頃、高木掃部の妻は花見に出かけました。その途中で落し穴に落ちていた子連れの狼を発見し、助けてやりました。 その後、妻が病気で亡くなると、妻の助けた狼が人間の女性に化身し、掃部の身の回りの世話をするようになり、やがて掃部も心を許し妻となります。妻となった狼は掃部とその家族を守り、また奪われた家宝の刀剣を奪い返します。しかし刀を取り返す際に受けた傷がもとで、いのち尽きてしまうのでありました。(参照:養父市HP「まちの文化財(105)」、他)
近くの養父神社では、狛犬ではなく狼が神社本殿を守っています。人と狼が密接に関係し、生活していたのでしょうか。
とはいえ奥様が狼で、それを知った掃部さんの驚きやいかに、、。う~む、空想が広がります。

もう一度八鹿駅を起点にして、今度は左側に歩を進めます。400mほど行くと右手に上る道があり、その道を更に150mほど行くと赤松広秀供養塔があります。
【伝説】
お堂の中にある自然石には、「乗林院殿可翁松雲居士之墓 慶長五年十月廿八日 三十三歳逝 前竹田之城主赤松左兵衛広秀」の文字が刻まれています。建立は元文4年(1739)です。
赤松広秀は関ヶ原の合戦で西軍につき、西軍が負けるとただちに東軍に味方し、西軍の鳥取城を攻めて降伏させました。しかし東軍大将の徳川家康は広秀を許さず、切腹を命じました。無念の広秀は怨霊となって鳥取城下に災害を起こし、鳥取の人々は赤松大明神として社を作って怒りを鎮めましたとさ。
赤松広秀が徳川家康に切腹を命じられたのが1600年(慶長5年)、139年もたってからお墓が建立されたことになります。お墓が建立された前年は大変な飢饉の年でした。しかし八鹿では広秀が養蚕を奨励していたので飢饉を乗り切れました。このご恩を讃えて供養塔が建立されたといいます。

赤松広秀供養塔から八鹿のウダツの上がる町並みを見て、更につるぎが丘公園に向かいます。但馬牛のレストランのところまで来ると箕谷古墳群の看板があります。(供養塔から約3.1km)
芝生がきれいに刈り込まれ、よく手入れがされています。石室を覗いてみると埋葬の状態が分かるように、人型が置かれていました。

箕谷古墳群から全天候運動場に向けて更にに1.5km、頑張って上がりましょう。運動場の道を挟んだ向かいに、おりゅう柳の伝説地である大きなくぼ地があります。ここには柳の大木があったと伝えられており、八鹿町高柳の地名のもとになったといわれています。
【伝説】
昔、高柳におりゅうという美しい女性が、夫や子供と住んでいました。おりゅうが長い髪をすくと、遠くにある大柳の枝が風もないのに、音をたてて揺れていたそうです。その頃、京の都では三十三間堂が建てられることになり、その材木に大柳が選ばれます。大柳を切り倒し始めましたが、翌日には驚いたことに切り口が見当たりません。何度やっても同じでしたが、木くずを焼くと切り口はふさがらず、やっと切り倒しました。柳を京へ運ぼうとしますが、今度はびくとも動きません。皆が困り果てた時、おりゅうの子が大柳の上によじ登りました。すると柳はするすると動き始めます。おりゅうは柳が切り倒されたその時刻に息を引き取っていました。おりゅうは柳の精だったのでしょうか、、。(参照:但馬の百科事典)
何と!! 八鹿駅周辺には、女性に身を変えた精霊が多いことですねえ。

ここまできたら、全天候運動場の管理棟(?)の渡辺うめ人形展を見ましょう。
農村のどこにでもあったであろう、喜びや悲しみとともに生活する人々の暮らしが、いきいきとした人形に表されています。
八鹿駅の周辺には、伝説に彩られたまちと人の暮らしがあります。皆さんもいかがですか?
但馬はいつでも、旅人を迎えてくれます。
電車で来られる方はこちらもご覧ください
「たじま途中下車の旅」~八鹿駅編~