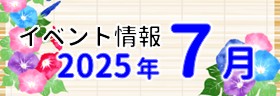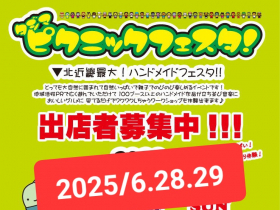21日土曜開催の「長谷(ながたに)万燈まつり」に参加してきました。いただいた資料によると「万燈」の由来は、近隣村との江戸時代初期からの山争いにあり、その時長谷村有利の証言をして、村に不利益を与えたと言われ、殴殺された隣村の黒兵衛の霊を供養することで始まったようです。今では考えられませんが、山は建築材は勿論のこと燃料の薪や刈敷肥料・牧草など村人の生活には欠かせない財産でした。

東にある万燈山山頂付近で行われていたのが、里におりて今では村内の農道で行われるようになりました。松明確保が難しく一時期灯油を使ったこともあるそうですが、やはり本物の松明(たいまつ)は値打ちがあります。夜8時前になると太鼓を合図に、道沿って立てられた「ちらし」(竹の先端の松明を挟んだもの)120本に点火されまると、水路に映った松明の火は幻想的な雰囲気を醸し出します。

次に子供達が火がついた「振り台」(細かく割った松明をまとめ蔓などでくくりつけたもの)を勇壮に振りながら皆が待つ公民館に向かって進みます。「ジリジリッと松脂(マツヤニ)が焼ける音と松明独特の香りを発しながら黒煙を上げて赤々と燃える・・・・」という表現がぴったりです。

この時期但馬では、関宮の万燈の火祭り、温泉町の火祭り、出石や竹田、日高町広井地区などあちこちに害虫駆除・五穀豊穣を願う火祭りが行われますが、山争いの犠牲者の慰霊が由来というものは珍しいでではないでしょうか?