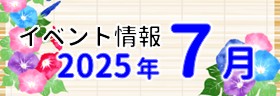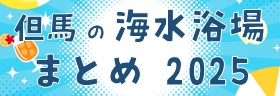タニウツギは但馬にお住まいの方なら必ず目にされている植物です。山地の日当たりのよいところにはごくごく普通に生えています。高さは最大で5mほどで、それほど大きくはなりません。4月末ごろから咲き始めますが、高い山では6月でも咲いています。

5月に山すそなどで薄いピンクの花が咲いていればこの木だと思ってもらえばまず間違いないでしょう。咲く前のつぼみは色が濃くて赤に見えるものもありますが、花びらが開くと大体薄いピンクになります。色の濃いものにはめったに出会えません。
 タニウツギのピンクと白が並んで咲いていた。
タニウツギのピンクと白が並んで咲いていた。

中には純白の品種があってシロバナウツギと呼ばれています。海岸沿いには多いように思いますが、山の中で見かけることもあります。いずれにしても多くはありません。

花は漏斗のような形で長さが3cmほどあり、先は5つに裂けています。花の直径は3cmほどです。雄しべは5個あり、花筒とほぼ同じ長さです。雌しべは1個で、花筒から少し突き出ます。雌しべの先にある柱頭は円盤のような形をしており、受精が終わったころには落ちてしまいます。
北海道の西部から本州に生育しますが日本海側に多いようで、兵庫県では淡路島にはわずかしか生育しません。そんなことで私は兵庫県の太平洋側には少ないと思っていましたが六甲山にはたくさんあるそうです。
タニウツギは、ウツギという名前ですが、タニウツギはスイカズラ科、ウツギはアジサイ科と大きく異なる植物です
 植栽
植栽
 武田尾
武田尾
兵庫県にはハコネウツギ、ニシキウツギ、ヤブウツギというよく似た仲間が生育します。但馬には南部を除くとタニウツギしか生育しませんが、ハコネウツギは各地に植栽されています。但馬のハコネウツギは植栽なので兵庫県全体でもそうだと思っていましたが、調べてみると太平洋側には自生もあるようです。
ハコネウツギの花は、咲き初めは白でやがて赤くなります。これはニシキウツギも同じで、ニシキは二色の意味で、白から赤になることを表す名前です。ヤブウツギは濃い赤です。タニウツギ以外は生育地が限られます。