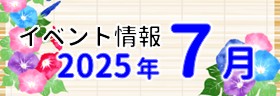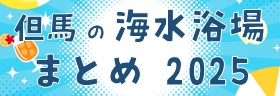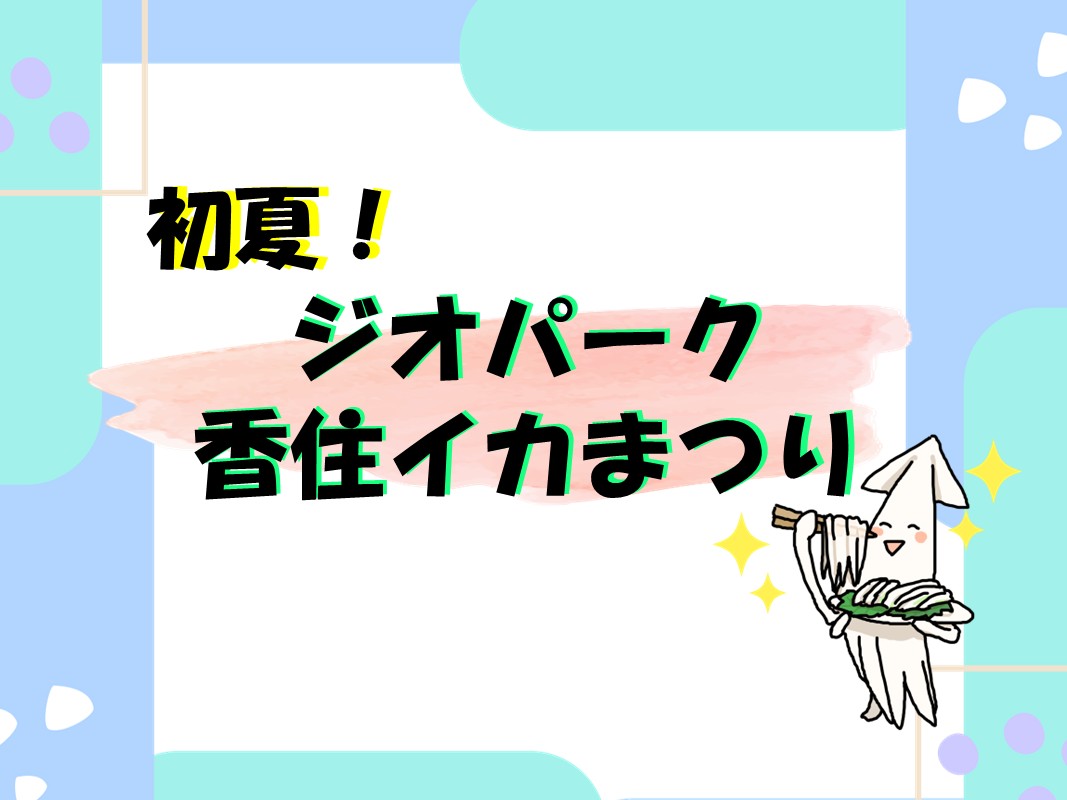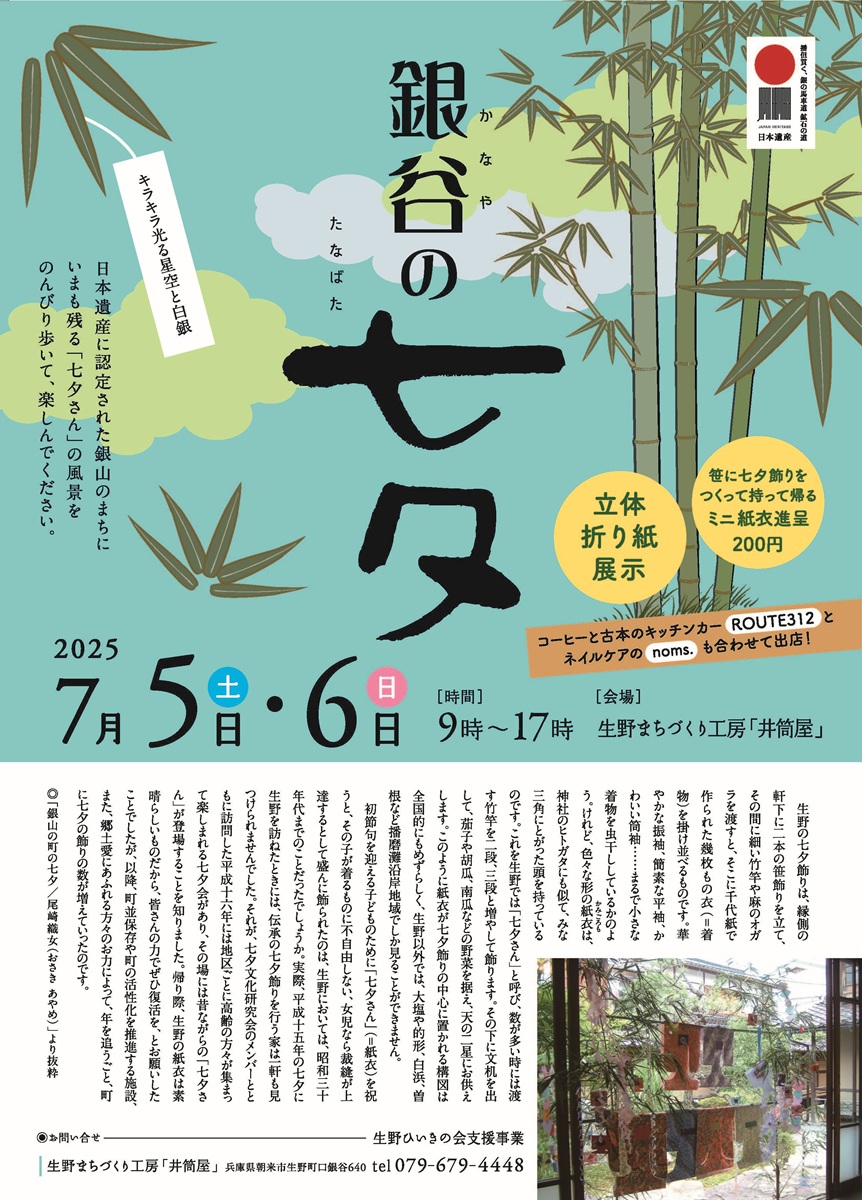雄株。雄花。
雄株。雄花。
ヤマアイ トウダイグサ科
日本では本州、四国、九州、沖縄に分布します。国外では朝鮮、中国、インドなど広く分布します。
山地の林縁や渓谷沿いなどのやや湿潤な場所に多いように思います。雌雄異株であるとも、ときに雌雄同株の多年草であるとも書かれています。この写真の群落は、ほとんどが雄花をつけた株で、雌花の株は一部にかたまって見られただけでした。種子で繁殖するだけでなく、白い地下茎を伸ばしても繁殖します。写真の地は雄株のクローンが広がっているのかもしれません。
 地下茎。掘り採って放置すると白い地下茎がやがて青黒くなる。絞った液は、青→赤になると言われている。水溶性なので布には定着しない。
地下茎。掘り採って放置すると白い地下茎がやがて青黒くなる。絞った液は、青→赤になると言われている。水溶性なので布には定着しない。

葉は対生し、光沢を持つ淡い緑色~深い緑色をしています。葉柄の基部には托葉がついています。雄花序は穂状で、雄花が5~11個つき、雄花からはたくさんのおしべが突き出します。雌花には2個の棒状体と1個の雌しべがあります。
 葉柄基部に托葉がついている。
葉柄基部に托葉がついている。
 雌株、未熟な果実。
雌株、未熟な果実。
 雄株、雄花
雄株、雄花
 タデアイ、栽培、美山かやぶきの里。
タデアイ、栽培、美山かやぶきの里。
ヤマアイは山藍です。藍というのは藍染めで有名な植物で、タデアイというタデ科の植物です。ヤマアイはタデアイと区別するためにつけられた名前だと言われています。ヤマアイは、日本最古の染料なのだそうです。「魏志倭人伝」に「倭国から赤や青に染めた絹織物が魏王に献上された」とあるそうですが、これはヤマアイで染められたものかもしれません。
ヤマアイは、タデアイが渡来するまでは利用されていましたが、やがて使われなくなり、利用法も忘れられてしまいました。しかし、染織家の辻村嘉一氏が苦労の末、昭和51年に、銅媒染で藍色が布に染着して、水洗しても落ちないことを発見されました。これが昔の方法かは分かりませんが、染料として利用できる方法が見つかったのです。
 この左右数10m、上にも10m近く生えている。
この左右数10m、上にも10m近く生えている。
近年、ヤマアイは増えています。場所によっては急増し、一面を覆うほどの群落となっていることもあります。写真の場所は数十mに渡ってヤマアイが続いていました。ヤマアイは、ニホンジカの不嗜好植物なのです。
かつては染色できるほど採ることは困難でしたが、今は簡単に採れそうです。一度試してみたいと思います。
 不嗜好なだけで食べられないわけではない。
不嗜好なだけで食べられないわけではない。