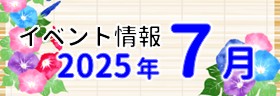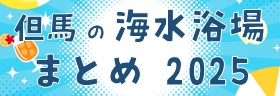オオムラサキホコリ

オオムラサキホコリ、単子嚢体型、束生し、有柄で高さ10~25㎜。子嚢は円筒形または上方に漸細し底部と上部はふつう丸く、紫褐色から暗褐色。
柄は黒色で光沢があり中空。軸柱は柄の延長で上方に漸細し、しばしば上部は屈曲して子嚢のほぼ頂端に達する。
表面網は太くてふつう刺はなく、連絡部は広がり、網目は丸みを帯びてとても粗く大きい。
胞子は直径7~9µmで細かい疣型。
春~秋に腐朽度が低い広葉樹の樹皮などにふつう。

2018年1月3日に「ムラサキホコリの一種(おそらくオオムラサキホコリ)」という記事を書いた。
https://www.tajima.or.jp/nature/others/119422/
調べてみると、但馬情報特急に初めて変形菌をメインに書いたのがこの記事である。読み返してみると、当時はとてもムラサキホコリの仲間の種同定ができるような知識がなかったし、キノコからの延長で変形菌に興味を持って観察をしていることがよくわかるような記事だと思う。写真のものも、「おそらくオオムラサキホコリ」と書いているが、そうではないものも混じっているように思われる。この時から7年ほどが経過して、自分なりに変形菌の知識も増え、今回は改めてオオムラサキホコリの記事を書いてみようと思う。

ムラサキホコリ目、ムラサキホコリ科、ムラサキホコリ属、オオムラサキホコリ。
オオムラサキホコリの特徴は、大きくて、歩きながらキノコ目で見つかる。キノコファンなら見たことのある変形菌ではないかと思う。

多くの変形菌は小さすぎて、キノコ目ではなかなか気が付かないが、オオムラサキホコリはふつうに見つかるのである。2~3㎝にもなる子実体は存在感がある。たくさんの胞子を飛ばしていて、マルヒメキノコムシ?などの変形菌の胞子が大好きな甲虫類がくっ付いていることが多い。

腐朽度の低い広葉樹の腐木の樹皮に発生しているのでよく見かける。我が家の庭の家庭果樹用クルミの枯木にも発生していたことがある。

前回紹介したムラサキホコリの胞子は網目型なのであるが、今回紹介するオオムラサキホコリは疣型である。網目型については生物顕微鏡の400倍でもそれなりに網目であることがわかるのだが、疣型の疣については400倍ではよく分らない。調べてみると私の顕微鏡が安物であるからというわけではなく、もともと400倍では観察が厳しくて1000倍で観察すべきということらしい。

頑張って1000倍で観察してみるとようやくそれらしいものが確認できた。1000倍で見ようとすると、100倍油浸レンズを用いるとか、プレパラートとレンズの間にオイルを入れるとか、いろいろと面倒である。いまいち良く分からないのであるが、光の屈折率の関係で、可視光線での光学顕微鏡では対物レンズ100倍が限界で、接眼レンズ10倍と合わせて1000倍とし、油は空気と屈折率が異なるので、対物レンズとプレパラート間を油で浸すことにより開口率が上がり、より多くの光を集めることができるので、像を明るく鮮明に見ることができるということらしい。いずれにせよ、400倍では疣は見えなかったが、1000倍では疣が見えるようになったのは確かである。しかし、1000倍となるとピントの合っているのはとても薄っぺらで厚さは1μmも無いようで、胞子の直径は5μmとか10μmとかあるわけだから、ピントが合って見えるのは球体表面の頂点の一部とか、赤道部分はなんとか見えるが中央部分はほとんどぼやけているとか、そんな風なので、図鑑に書いてあるイラストのように全体がきれいに見えるということはないのである。それをさらに低速度でブレブレに写真撮影するものだから、ぶよぶよの画像になってしまう。ということで、とても分かりにくい写真ではあるが、オオムラサキホコリの胞子の顕微鏡写真を掲載しているので、疣型であることを見てもらえれば幸いである。胞子表面の模様については1000倍でないと見ることは難しいのであるから、今後は、横着はせずに1000倍油浸による観察を行いたいと思う。

掲載した写真は、オオムラサキホコリと同定した3標本より採用した。子嚢の表面にほぼ完全な表面網があり、樹上生、胞子は疣型、表面網の網目は30-100μm、胞子の直径は7-9μmなどよりオオムラサキホコリと同定したものである。


表面網は太くてふつう刺はなく、連絡部は広がり、網目は丸みを帯びてとても粗く大きい。