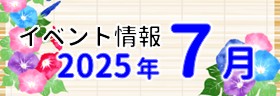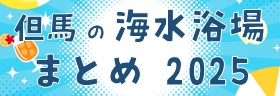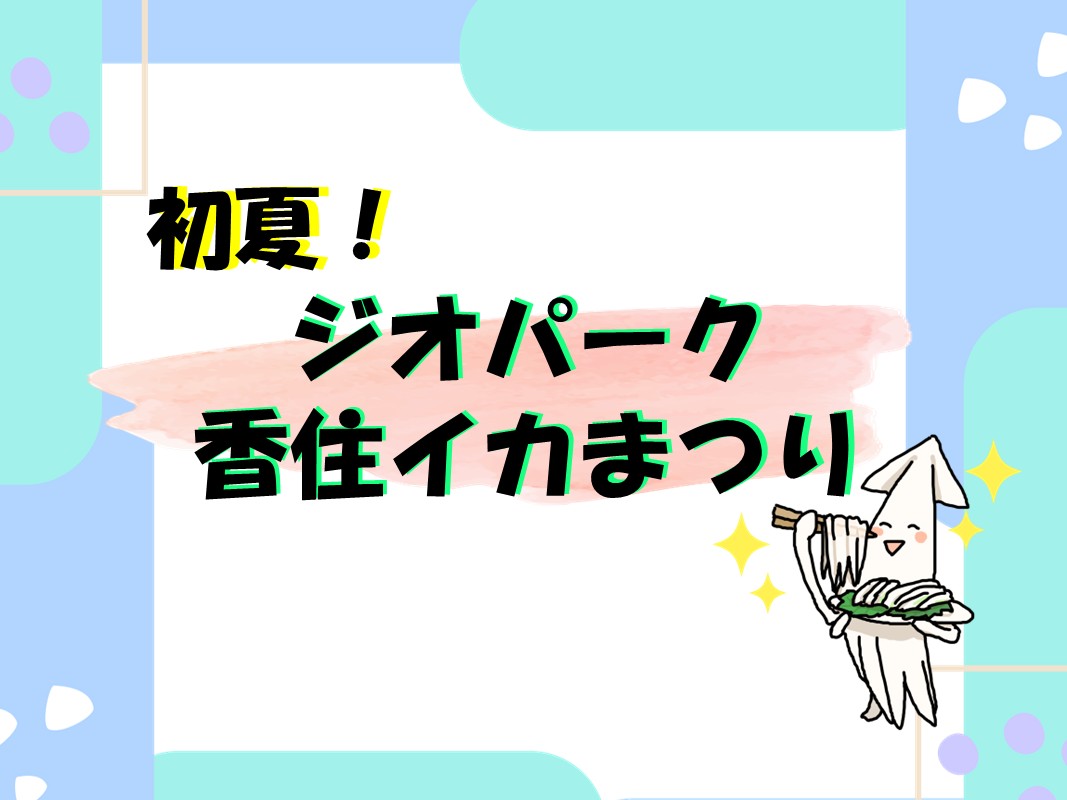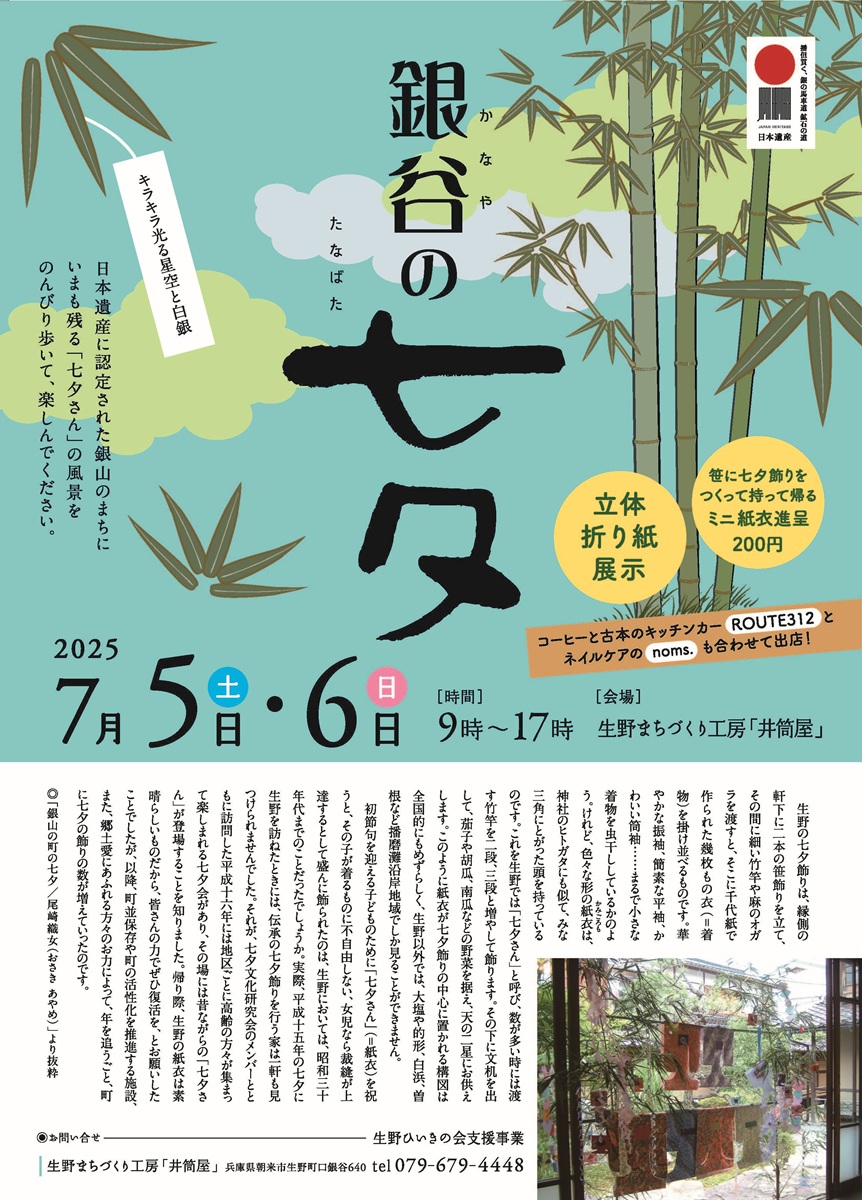トビゲウツボホコリ、和名は「とび色の毛のウツボホコリ」という意味だろうか、成熟した子実体は褐色でトビ色のイメージだ。変形体は見たことは無いのだが桃色・赤色または白色とのこと。

子実体は単子嚢体型、群生または密生し、成熟しても4㎜程度。子嚢は若い時は鈍橙色・桃色または赤褐色でやがて退色して暗褐色になる。

短円筒形から卵型で短い柄を持ち浅い杯状体に載り、胞子をぎっしり抱えた細網体は管状で分岐し網を形成し、杯状体から離れやすいことが特徴的で、しばしば一団となって落下する。ここまでは、図鑑に記載されている内容を基本に、私なりに乱暴に要約したものである。

さて、ここからが今回私が観察して記載する内容で既存の資料では書かれていないのではないかと思われる内容である。

しばしば一団となって落下するといっても完全にではなく、1から数本の細網体糸が杯状体と繋がっている場合が多い。このことは、最新の図鑑である日本変形菌誌(2021年、山本幸憲、日本変形菌誌製作委員会)の図からも推察できる。

先日、標本を採取した時に、若い一団の子実体が二つに分断されてしまったのだが、その際にいくつかの細網体が杯状体から落下した。このこと自体はトビゲウツボホコリの特徴をよく表している現象だと思うが、後から拡大写真を見てあることに気が付いた。脱落した細網体の多くは一本の細網体糸で杯状体につながり、あたかも端が結ばれた毛糸の玉が転がっているように見えるのだ。見事なぐらいに。

その写真をフェイスブック粘菌グループで報告したところ、「もしかしたら、ほぐしていくと一本の細網体糸でできているのではないか」、との冗談めいた話が出たのであるが、確かにそういう想像を湧き立てるところがある。
さすがにそんなことは無いにしても、この現象には何か理由があるのではないかとの強い興味を感じたのである。その後2日間現場を訪れて観察を続けたところ、自分なりに明確な理由が分かった。明確な理由というのは、掲載した動画をご覧いただければ一目瞭然と思う。すなわち、トビゲウツボホコリは細網体糸でぶら下がって、少しの風でゆらゆら揺れて、胞子を飛ばしやすい状態にして、子孫繁栄に努めているのだ。

トビゲウツボホコリは子実体を形成すると、甲虫類を誘引する物質を出し甲虫類を呼び寄せる。甲虫類がもぐりやすいように子嚢の下に少しの柄を持っておりそこへ迎え入れる。もともと杯状体から外れやすい細網体の塊は、もぐりこんだ甲虫類の刺激で胞子をぎっしりと抱え込んだ状態で杯状体から脱落する。

しかし、1~数本の細網体糸がしっかりつながったままなので、あたかも毛糸玉がぶら下がった様な状態となる。それがわずかな風にもゆらゆらと揺れて、胞子を拡散させてゆく。。。。そういう戦略なのだ。たぶん。

面白いやり方だと思う。

細網体と胞子