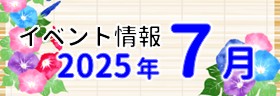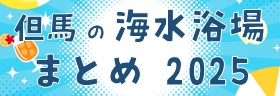今年はキノコが豊作

今回は、9月以降に撮影したキノコたちの一部を紹介する。毒キノコと安全に食べられるものが混在しているのでご注意してください。
秋のキノコシーズンもいよいよ本番。但馬の山には致命的な毒きのこも、普通にたくさん生えている。野生キノコを食べることは大変危険なので、確実なもの以外は食べないこと、美しいキノコたちを鑑賞して楽しみましょう。

中毒例の最も多い毒キノコの一つ。見た目がおいしそうで、食菌のウラベニホテイシメジにわりと似ていて、同じような場所に発生する。胃腸系の激しい症状がでるが致命的ではないようだ。

木の根元から出ていることが多い。名の通り興奮し、幻覚症状が出る毒キノコ。致命的ではない。苦いので毒成分と合わせて処理して食べる地方もあるらしい。歯ごたえは良さそうで、多収穫が見込めるので、適正な処理方法をとれば結構優秀な食菌になるのだと思う。

放尿跡などに発生しやすいアンモニア菌。歯ごたえが良い。食。もしかしたらカレバキツネタケかもしれない。

30センチぐらいになる大きなキノコ。カラカサタケなどよく似たものが数種類あり、多くは食べられるが、毒のものもある。

見た瞬間、チシオタケと思ったが、傷つけても赤い液が出ない。クヌギタケは通常灰褐色だが、淡紅色を帯びる場合もあるようなので、クヌギタケとした。食。

マッシュルーム(ツクリタケ)の仲間。食用菌とされていたが、人によっては強い胃痛をおこすことがあるようで、最近は毒きのことされている。

猛毒菌の多いテングタケ科の仲間だが、美味しい良菌。わかりやすく、間違いにくいのが良い。

猛毒菌の多いテングタケ科の仲間。良菌のタマゴタケとともにテングタケ科の中では比較的安心して食べられるが、生食は中毒するらしい。樺色(茶色)であることが重要。同じ形で灰色系のツルタケも同様に食だが、紛らわしい毒菌が多い。

テングタケ科の毒キノコ。激しい下痢等胃腸障害や幻覚症状が出るらしい。致命的ではないようである。毎年その辺にたくさん生えている。

猛毒菌の多いテングタケ科の仲間。古い図鑑では美味しい食菌と書かれているものもあるが、生食は中毒するようで、紛らわしい猛毒菌も多いのでやめた方が良い。

イグチの仲間(ざっくりいうと傘の裏がヒダではなく網目状になっている、カサと軸がはっきりしている菌根菌の仲間)は、毒きのこは比較的少なく、昔はイグチに毒きのこはないといわれていたが、近年致命的な毒きのこが見つかっている。また、消化不良を起こしやすいものや、苦くて食用に向いていないものも多い。このゴビチャニガイグチは名前とは違い苦くないとのこと。毒性も確認されていないようだが、私はまだ食べたことがない。

イグチの仲間で、軸に特徴がある。かっこいいと思う。食。

大型のイグチ。カサの模様が特徴的。存在感の強いキノコ。虫が入りやすいが、広義のポルチーニ、優秀な食菌。


大型のイグチ。全体に紫色であるが、カサに黄色が入るものがあり、時に大部分が黄色っぽものもある。これも広義のポルチーニ、優秀な食菌。




イグチの仲間。広葉樹林の地上に発生。群生していた。食。

赤系のイグチはたくさんあるが、このベニイグチがもっとも鮮やかで深みもあり美しいと思う。食。個人的に大好きなイグチ。

橙色の美しいイグチ。小さいが山中でよく目立つ。食。


少し赤色系で、強く触ると青色に変性するイグチはたくさんあって難しい。胃腸系の中毒を起こしやすいものが多いとされている。

赤が美しい。種はよくわからない。

イグチ科に分類されているが唯一ヒダ状のもの。黄色がきれい。体質により軽い胃腸系の中毒を起こすようだ。

ベニタケ科の仲間はいろいろなよく似た種類があり、紅色のこの手の種の特定はかなり難しい。食べられるもの、苦いもの、毒のものいろいろあるようだ。ドクベニタケが名前としては有名。


ベニタケの仲間で緑色の美しいキノコ。食。

地面に茶色い胞子の塊。熟すと、皮が破けて胞子が散乱される。若いうちは食べられる。

種の同定については間違もあろうかと思います。また説明についても、ざっくりと記載しておりますし、認識間違いがあるかもしれません。見解の相違はあろうかと思いますが、明らかな間違いについてはご指摘いただければと思います。


乾燥させると、カサも減って保存しやすく、さらに味もよくなる場合が多い。