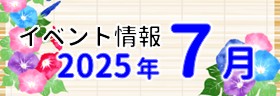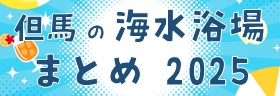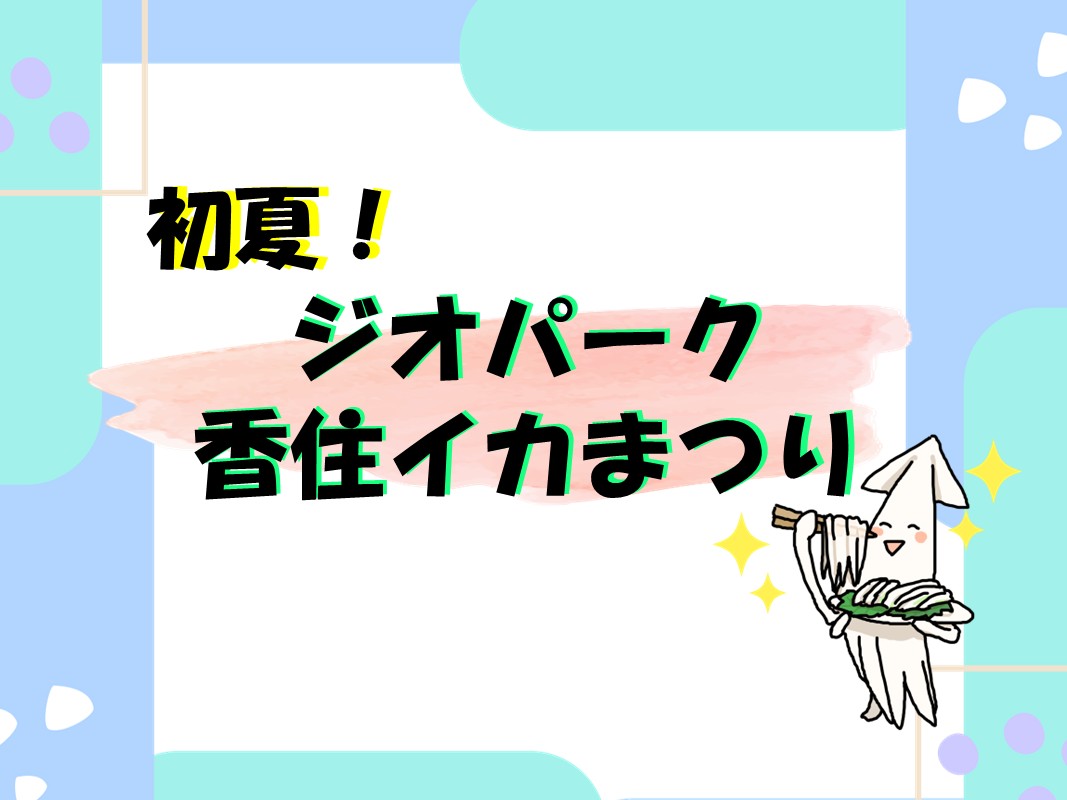ヒノキオチバタケ

ヒノキの人工林を歩いても、一年を通してあまりキノコは出ていない。キノコ探しから言うとあまり面白くないエリアだと思う。

しかし、6月下旬の兎和野高原のとあるヒノキ林の足元、小さな白い花が咲いたようになっていた。梅雨の合間にヒノキオチバタケが一斉に発生したようだ。

新鮮なヒノキオチバタケは小さくて白くて美しい。傘の径は0.5~1cm程度、扁平で縁部内巻き、表面淡灰色微粉状に放射状の浅い条溝がまばらにある。柄は2~3.5×0.1㎝。

学名を見るとHongoと付いているから、日本の偉大な菌類分類学者である本郷次雄先生が命名されたのだろう。

ホウライタケ科シロホウライタケ属。ホウライタケの仲間は、食用の価値はないが、小さくてかわいらしいものが多い。

ヒノキオチバタケはスギ、ヒノキ、アカマツなど針葉樹の落葉、落枝、球果などに群生する。山と渓谷社の図鑑「日本のキノコ」の写真では、杉の葉から出ているものが掲載されている。ヒノキオチバタケというくらいだから、ヒノキから発生しているものを紹介したい。

なぜか途中で葉っぱや小枝に癒着しているものを多く見かける。どういう風にしたらこうなるのだろう。

ヒノキオチバタケは全体的に薄い皮質なので、新鮮な時はみずみずしいのだが、傷みにくいものの少し干からびたようになってくる。

なお、分類の基準はこれまで山渓の日本のキノコに準じていたが、今回は北隆館の「新分類キノコ図鑑」に従った。