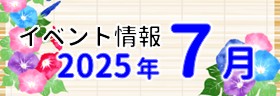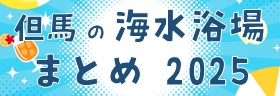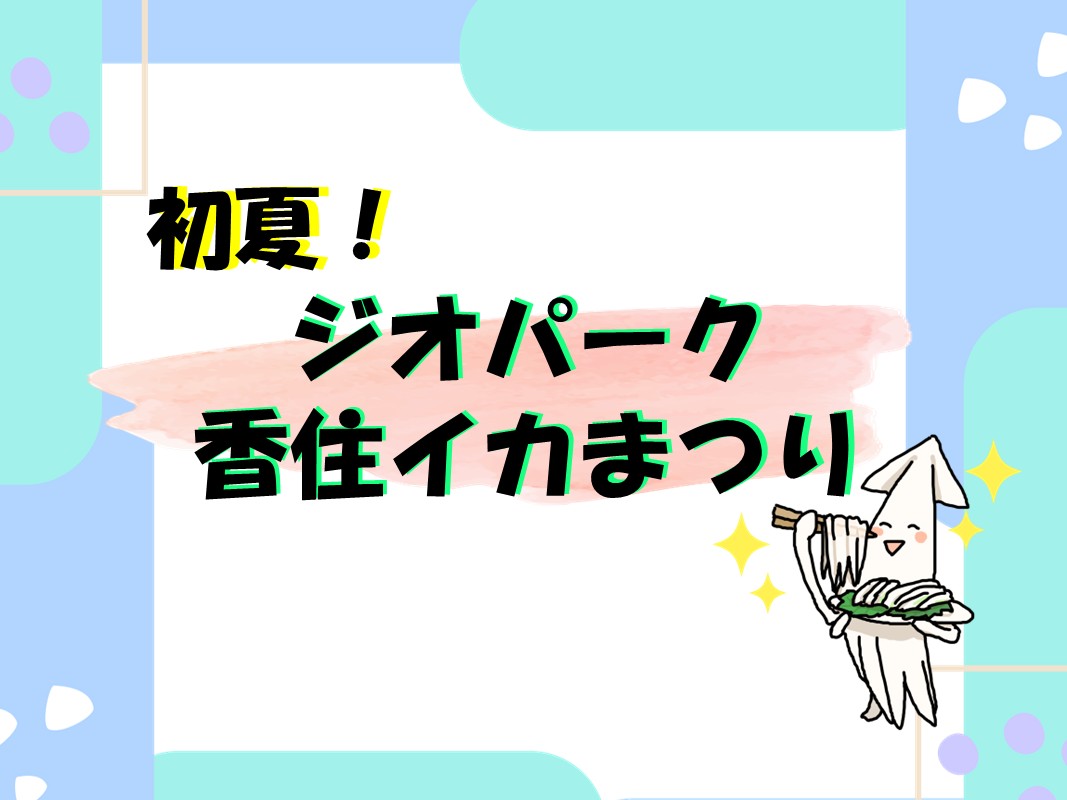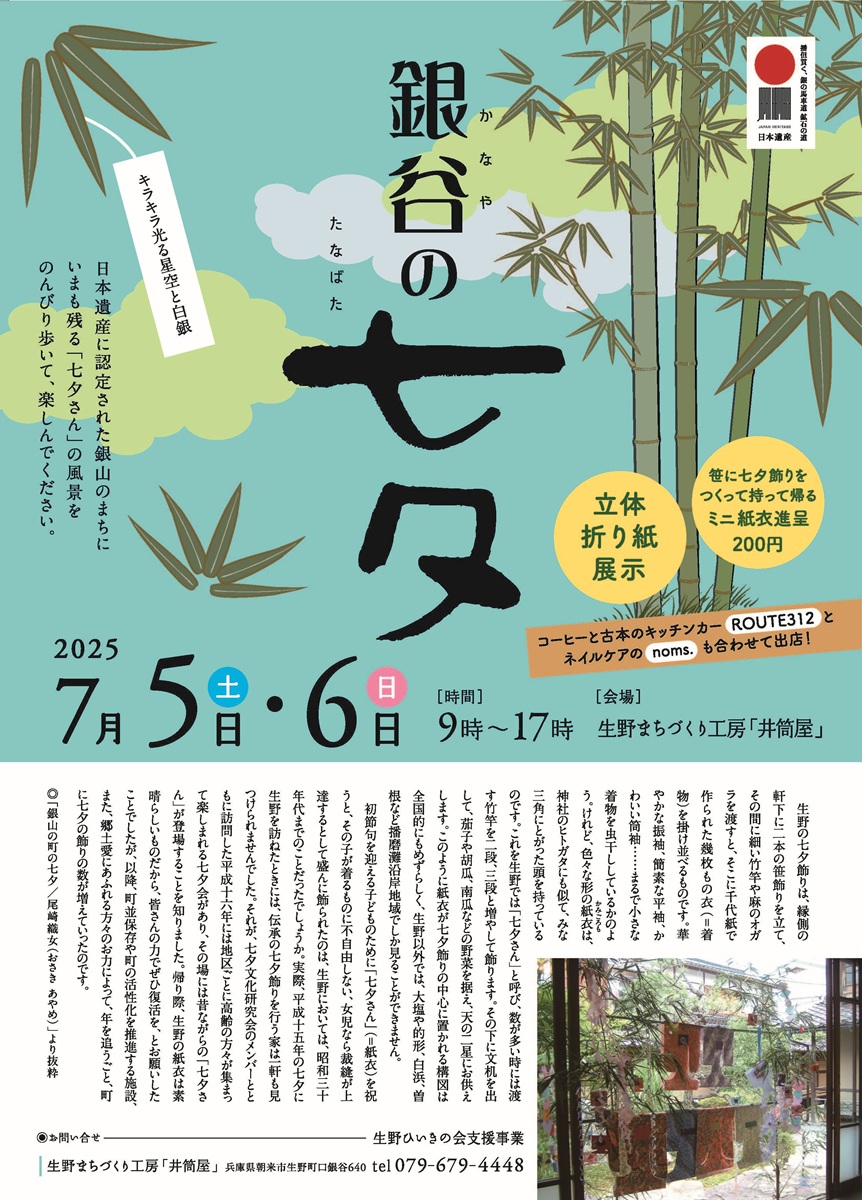春を待つ植物たち
翌日から雪が降るという天気予報でしたので、春を待つ植物を探しにちょっと散歩をしてみました。
歩いたのはこんな場所です。左側には背の高い草はありません。右側の背の高い草は冬の間に枯れてしまい、降り積もった雪で押し倒されています。左側には枯れた草がありません。これは草刈りのおかげです。気持ちのよい空間はどこも人の手でお世話がされているのです。
非常に身近な植物を紹介しますので、雪がとけたら観察してみてください。

3種類の植物が生えています。一面に広がっているのはシロツメクサです。これ以上背は高くなりません。草刈りがないと絶えてしまうでしょう。わずかにヒメオドリコソウとノボロギクが生えています。こちらは背が高くなりますが、それでも草刈りがないと数年で姿を消すでしょう。路傍の草には、人の日々の暮らしが大きな影響を与えています。

先の写真にわずかに写っていたヒメオドリコソウです。気の早い個体は、上に伸びる前に花を咲かせていました。ヒメオドリコソウは外来種です。至るところに生えています。

こちらはオドリコソウです。在来種です。激減しています。最初の写真の右側の枯れたススキがまばらに生えているところに生き残っています。線路の法面なのですが自然度が高いのでしょう。他にも在来種が多く生えています。

これはホトケノザです。秋の小春日和の頃からたくさん咲いていました。在来種です。ヒメオドリコソウとちょっと似ていると言う人もいます。雪で倒されてまだ起き上がれていません。

皆さんもよくご存じのヨモギです。もう少し大きくなったらよもぎ餅を作るために摘みます。
私の祖母が亡くなってもうすぐ50年になります。ということは我が家でよもぎ餅を作らないようになって少なくとも50年以上経つということになります。イベントでは何度か作っているのですが、家で作る、そんな余裕がほしいなと思います。

ブタナです。地面に張り付くようにして放射状に葉を広げています。こんなのをロゼットと言います。地面は温かいし、日の光を存分に浴びることができますし、合理的な姿なのです。各地にはびこる困った外来種です。

ノゲシ(ハルノノゲシ)です。在来種です。よく似たのが何種類かありますが、ノゲシの仲間としておきましょう。

アメリカフウロでしょう。外来種です。昔は、この植物が生える場所には普通にゲンノショウコが生えていたのですが、今は、まず見ません。

ヤハズエンドウ(カラスノエンドウ)です。この時期のヤハズエンドウの葉は、面白いです。丸いのや細長いのが混在しているのです。原因はなんなのでしょうか? この植物は、食べられます。私的には、美味しいです。

ヒガンバナです。
この田んぼの周りにだけ残っているので、地権者の方が意図的に残されているのですね。花を愛でる想い、尊いと想います。

多分、ケキツネノボタンです。果実ができないとキツネノボタンと区別ができません。難しいです。

オオイヌノフグリです。外来種です。3月になって咲きそろうととても美しいです。

オランダミミナグサです。外来種です。自然度の高いところにいくと在来種のミミナグサも見られます。

ナズナです。在来種です。春の七草の一種です。こんな実がつくともう美味しくないと思います。地面に張り付いているのが上に伸び始めた頃が食べ頃ではないでしょうか?

ジャノヒゲです。この時期、濃い青の美しい実がついています。ササでこの実を飛ばす鉄砲を作ってみましょうか?

テストです。
3種類あります。全て、これまでに出てきています。さあ、なんでしょうか?

最後に、これは、あかんやつです。
オオキンケイギク。特定外来生物です。日本の自然環境に顕著な悪影響をもたらす植物です。駆除する必要があります。