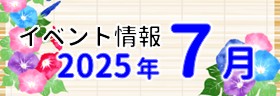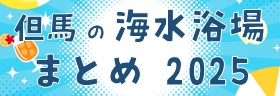ダンドボロギク キク科
この植物は各地で嫌われています。
私の所にも何カ所からか相談が来ました。
曰く「こればっかり増えて困る。」「みすぼらしくて困る。」「綿毛が洗濯物について迷惑だ。窓を開けられない。」・・・・などです。そして駆除の方法を教えてほしいと。
残念ながら私は駆除の方法を知りません。
現状では、そのままにしておいた方が無難ですよとお答えしています。
 これはまだ美しい方。秋になって植物体が茶色になり、そこに白い冠毛が残っていると本当にみすぼらしい。
これはまだ美しい方。秋になって植物体が茶色になり、そこに白い冠毛が残っていると本当にみすぼらしい。
ダンドボロギクのダンドは愛知県の段戸山に由来します。この山で最初に見つけられたのです。1933年のことだそうです。ダンドボロギクはその山で見つかった新種というわけではありません。ダンドボロギクは北アメリカ原産の外来種です。ボロギクのボロはもちろん襤褸です。襤褸は「使い古して役に立たなくなった布。ぼろぎれ。」のことです。この植物の花の咲き終わった後に出てくる冠毛を見るとまさしく襤褸です。特に雨に打たれた後はみすぼらしくて、抜きたくなる気持ちはよく分かります。
 近藤伸一氏撮影。
近藤伸一氏撮影。
 かなり深い山の中。
かなり深い山の中。
 耕作放棄田。
耕作放棄田。
ダンドボロギクは、先駆種と呼ばれる植物です。山肌があらわになるようなこと、植林の皆伐、山火事、土砂崩れ、・・・などが起きると真っ先に生えてきて一面を覆い尽くしたりする植物です。そして数年経つといつの間にか姿を消してしまう植物です。ダンドボロギクは、ほかの植物との競争に弱く裸地以外では次世代を残しにくいのです。
私たちがケガをするとかさぶたができて傷口を塞ぎ、傷を乾燥から守ってくれます。先駆種は、かさぶたと同じように山肌を覆ってそこを守り、次に出現する植物たちのための環境を準備してくれます。ダンドボロギクが生えてくることには、重要な機能があり、意味があるのです。
 ダンドボロギクは花が上を向いて咲く。
ダンドボロギクは花が上を向いて咲く。
ダンボボロギクは放置しておくと数年で姿を消すはずです。ところが相談に来られた方のお住まいの所ではダンドボロギクは一向に衰退せず、むしろ広がっています。自然に任せておくと消えていくはずのダンドボロギクが増えているという不思議なことが起きているのです。原因はシカによる食害です。増えすぎたシカは植物を食べて裸地を作ります。一方でダンドボロギクは嫌いなようで食べ残してくれます。シカがダンドボロギクに適した環境を維持管理してくれているのです。
 よく似たベニバナボロギクは花が下を向いて咲く。若葉はシュンギクの味がして結構おいしい。シカはこの味が苦手なのではと思う。
よく似たベニバナボロギクは花が下を向いて咲く。若葉はシュンギクの味がして結構おいしい。シカはこの味が苦手なのではと思う。
こんな状況でダンドボロギクを駆除と称して抜くことは、ダンドボロギクのために好適地である裸地を作ってやっていることになります。また、裸地を作ることは、土砂崩れを誘発することにもなります。ここは辛抱してダンドボロギクを生えしておくしかありません。
 黄色;ダンドボロギク、赤;ベニバナボロギク、水色;レモンエゴマ、白;イワヒメワラビ。他のシダはワラビ。
黄色;ダンドボロギク、赤;ベニバナボロギク、水色;レモンエゴマ、白;イワヒメワラビ。他のシダはワラビ。
ここまで悲観的なことを書いてきました。
しかし全く解決策がないわけではありません。一番の方法は狩猟や有害獣駆除でシカの生息密度を下げることです。シカの密度が下がれば他の植物が生えてきてダンドボロギクは消えていきます。次の方法は、ダンドボロギクのようなシカの不嗜好植物の中からよりましな種類を探して植えることです。候補としては、エゴマ(レモンエゴマ)やイワヒメワラビやマツカゼソウがあります。実際、コウノトリの郷公園では、ダンドボロギクがベニバナボロギク、レモンエゴマ、イワヒメワラビと一緒に生え、襤褸が目立たない場所があります。いずれにしてもダンドボロギクを減らすのは長く厳しい戦いになります。