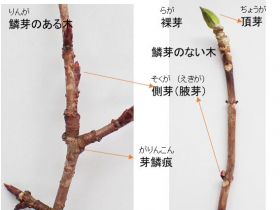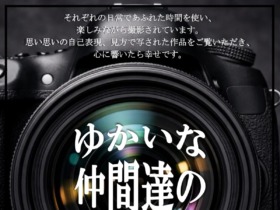ヒダマウツボホコリ

前々回はウツボホコリ属のタイプ種であるウツボホコリについて、前回はウツボホコリと紛らわしい種の一つであるウスベニウツボホコリについて書いた。
今回はさらにもう一つウツボホコリと紛らわしい種、ヒダマウツボホコリについて書いてみたい。これも専門家により同定していただいた標本が確保できているので、それなりに信頼性のある記事が書けるのではないかと思う。
なぜ専門家による同定済みの標本が手元にあるのかというと、ウツボホコリについてはよく似た種がいくつもあるので、きっちりとした種の判定ができなくて困っていたのであるが、手持ちのウツボホコリ属の紛らわしい複数の標本を専門家に判定してもらう機会に恵まれたのである。ウツボホコリを中心に何種類か含まれているだろうと予想していたのであるが、結果はウツボホコリ、ウスベニウツボホコリ、ヒダマウツボホコリの3種類であった。中でもヒダマウツボホコリは、「日本変形菌誌」(山本幸憲 日本変形菌誌製作委員会2021年)で「稀」とされている種なので驚いた。ヒダマウツボホコリについては、図鑑で知っていたし、何やらかっこよい名前であるので気になっていた種であるが、実物はもちろん見たことはなく、図鑑のイラストでしか知らない。ネットで検索しても、現時点ではまともな画像は見当たらない。もしかすると、かなり慣れた人でないとウツボホコリやウスベニウツボホコリと区別するのは難しいかもしれない。今回は、そんなヒダマウツボホコリについて紹介したい。

ヒダマウツボホコリ。子実体は単子嚢体型で、やや群生し、有柄で直立し高さ1~3㎜程度。伸長して3.5㎜程度まで。子嚢は球形~広卵形、稀に短円筒形、赤色から緋色、直径0.4~0.7㎜。杯状体は深く大きい。柄は赤褐色から黒色で0.3~1㎜程度。細毛体は管状で分岐連絡し網を形成、網目はやや大きい。細毛体は杯状体から容易に離れると日本変形菌誌には書かれており、検索の基準にもなっている。しかし、強く付着するとされているウスベニウツボホコリの標本と比較しても私には差はよく分からなかった。細毛体糸は直径3~4µm、半環状、環状、疣状、または網状紋がある。胞子は直径6.5~8µm、数個の疣が散在。秋または春に腐木上に稀。

*写真は未熟な状態で乾燥してしまった子実体?
手持ちの標本や、写真などを見ながら、「日本変形菌誌」(山本幸憲 日本変形菌誌製作委員会2021年)の分類基準、検索表に基づいて同定作業を進めてみる。子嚢壁は上部まで残存しているものではなく「基部のみ残存性」。ここまでは良いが、細毛体は杯状体から容易に脱落するかどうかが良く分からない。強く付着するというほどでもないが、トビゲウツボホコリのように容易に脱落することはない。よってウツボホコリ属検索表のBかCの判断はつかない。子嚢は桃色または赤色を帯びており、顕微鏡で胞子を見れば、胞子の直径が6.5~8µmなので、検索表Cから該当するものを探せば、ウスベニウツボホコリ、ウツボホコリ、コウツボホコリのどれかということになるが、杯状体の形状が深く大きいことなどが一致しない。そのため検索表Bで進めることとすると、胞子の直径は9μm以下で細毛体が塊状に脱落することは稀、伸長した細毛体は球形から短円筒形、子嚢は緋色、子嚢壁はやや残存性(比較対象となる早落性のモモイロウツボホコリとは明らかに異なる)であることから、ヒダマウツボホコリと同定した。

*写真は若く細網体が伸長していない子実体
「細毛体は杯状体から容易に脱落する」検索表B、「細毛体は杯状体に強く付着」検索表Cという検索基準は、かなり主観的で難解であると思う。「細毛体は杯状体から容易に脱落する」という検索表Bの中で、「細毛体は塊状に脱落することは稀」という検索基準が出てくる。ということは、塊状ではない状態で容易に脱落するということと推察されるのであるが、それがどういうことなのか私には想像できない。

*写真は2021年採取の標本を今回撮影したものであるため色合いが褪せている。
ヒダマウツボホコリの大きな特徴の一つは、杯状体の大きく深い形状であると思う。子嚢の高さの半分程度までと深い。ただし、杯状体の形状はなかなか確認しにくいので、図鑑のイラストに示されているような深い杯状体を見ることは簡単ではない。

子嚢は球形~広卵形で、伸長しても3.5㎜程度までと、要するに長細くならずに丸っこいのも特徴である。

時に残存した子嚢壁がべっとり緋色を呈していたりしていたりすると、それがいかにも「緋色の玉」をイメージさせてくれる。

ところが、成熟するにつれ子嚢壁はなくなり、細毛体が伸長し短円筒形となり、緋色は色褪せ、同じくウツボホコリやウスベニウツボホコリの成熟したものと見分けが難しくなってくる。

ウツボホコリの仲間は顕微鏡により細毛体を観察すれば同定作業の決め手を得ることができる場合が多いようであるが、ヒダマウツボホコリの場合はそうでもないように思う。少なくとも私には難解である。今回はウツボホコリとウスベニウツボホコリが比較対象になった。ヒダマウツボホコリの細毛体は日本変形菌誌には「細毛体糸は直径3~4µm、半環状、環状、疣状、または網状紋がある。」と記載されているのだが、このことから、ウツボホコリ、ウスベニウツボホコリと明確な違いを見分けることはなかなか難しいように思う。ヒダマウツボホコリは、ウスベニウツボホコリのように疣状突起先端が金槌状になっているものが多くなく、ウツボホコリのように疣状、歯状、刺状、環状紋が混在していないということだと解釈しているのであるが、それを実際に検鏡して見極めることは私には難しい。

以上ヒダマウツボホコリの同定作業についてくどくどと書いてきたが、「子実体は伸長して3.5㎜程度まで、子嚢は球形~広卵形、短円筒形、赤色から緋色、杯状体は深く大きい。細毛体糸は半環状、環状、疣状、または網状紋がある。胞子は直径6.5~8µm、数個の疣が散在。」この辺りを落ち着いて確認していけば、たどり着けるのではないかと思う。また、状態のよいタイミングで、和名の由来となる緋色の玉をイメージできるような子実体を採取できれば同定は容易かもしれない。

*写真は2021年採取の標本を今回撮影したものであるため色合いが褪せている。
フィールドでは赤~褐色のウツボホコリの仲間にはよく出会うが、類似種が数多く存在する。見分け方が難しいので、フィールドでの種の特定を行うことは避けられ、「ウツボホコリの仲間」とか「ウツボホコリ属の一種」とかで済まされる場合が多い。ナガウツボホコリ、アッサムウツボホコリ、クロエウツボホコリ、ベニシロウツボホコリ、タレホウツボホコリ、クリゲウツボホコリ、、、赤~褐色のウツボホコリ属は多種である。もしかしたら知らない間にその地域での未確認種を採取しているのに見逃している可能性もあるだろう。やはり、こまめに標本を採取しておくことが重要である。今回は2019年に豊岡市で採取した標本が5年後の2024年にヒダマウツボホコリとして同定され、但馬地域初確認種として記録されたのである。